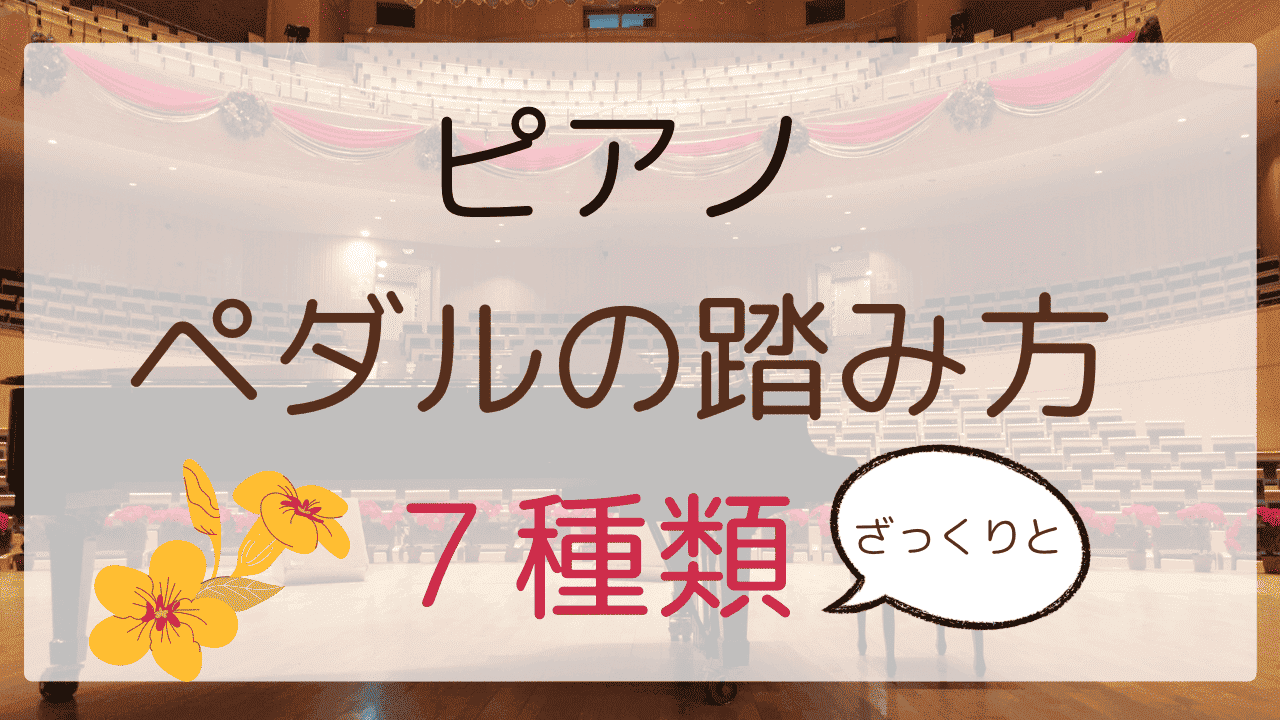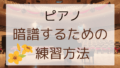ピアノのペダルは『耳で踏む』とよく言われます。
それは、音の響きをよく聴いてその時に使い分けたりするからです。
よく響くホールだったっらペダルは少なめにするなど
場所によっても使い分けます。
それはタイミングと深さで調整します。
深さはざっくりと
①1番下まで踏む、②半分踏む、③ごく浅く踏む
踏み方はざっくりと7種類にわけてみました。
(右のペダルについてです)
ペダルの踏み方
①打鍵の前から踏む
曲の初めの音に「何か足りない」と感じることはありませんか?
全く踏まなかったり、打鍵と同時に踏んだりすると「何か足りないな」と感じたら、試しに打鍵の前から踏んでみるとしっくりくるかもしれません。
硬さが取れ、柔らかい雰囲気になりますし、響きが豊かになります。
例として
ショパンのバラード4番
シューマンのトロイメライ
ドビュッシーの月の光 など
曲の始めや、曲の雰囲気が変わる始めのところなどによく使います。

②打鍵と同時に踏む
打鍵と同時に踏む例はたくさんあります。
ワルツの曲の拍の頭で踏んだり、1拍目だけ、1と3拍目だけ打鍵と同時に踏んだりすることが多いです。
また、アクセント記号のあるところで瞬間的に同時に踏むこともたくさんあります。
これは『アクセントペダル』といって、その音だけに少し気持ちを乗せたい時に打鍵と同時に踏み、すぐに離します。
リズムやテンポをとる際、助けになることがあります。
③打鍵の後に踏む
打鍵の後から踏むにも大きく分けて2通りです。
①打鍵の後にすぐ踏み込む→よく使われる基本的な踏み方。
②打鍵の後に音を聴いてゆっくり踏み込む
②は例えば
二分音符(2拍のばす)だったら、1拍目に打鍵して2拍目くらいに踏み込む。
四分音符(1拍のばす)だったら、1拍目に打鍵して1.5拍目くらいに踏み込む。
これを打鍵した音をよく聴いて踏み込みます。
④cresc.のペダル
ペダルを踏むと音の響きが増えていくのを利用します。
例えば、ペダルを踏みっぱなしでドレミファソと弾くと
前の音がどんどん足されて響きます。
音が足されるので音量的には、だんだんと大きくなりますよね。
この響きを足していってcresc.をしていこう、というペダルです。
ですので、cresc.のところで浅くから音を聴いながら徐々に深く踏み込みます。
音が濁ってきたなくなってないか注意が必要です。
⑤dim.のペダル
cresc.ペダルの逆で、深く踏んでいたところからペダルを徐々に浅くしていきます。
響きが弱くなって音を削ぎ落としていくイメージです。
音の響きを徐々に薄くしていきます。
⑥ハーフペダル
ペダルを浅く踏みます。
前の音の響きを少し残しながら、踏み換えを浅くしたり
しっかりと踏み換えた後に浅くしたりします。
時には
ビブラートをかけるように、浅く細かく響きを落としていくように踏み替えたりします。
⑦ロングペダル
楽譜に何小節もペダルの踏みっぱなしの指示があったりします。
昔のピアノは今のピアノより音が伸びなかったので、
作曲家はそのように指示をしていたようです。
現代のピアノは音がよく伸びるので、指示のまま踏みっぱなしにすると😭
音の響きを耳でよく聴いて、汚くなった響きを少しずつ削っていきます。
その時にもハーフペダルを使って音を少しずつ消していったりします。
まとめ
①打鍵の前から踏む
②打鍵と同時に踏む
③打鍵の後に踏む(すぐ・ゆっくり)
④cresc.のペダル
⑤dim.のペダル
⑥ハーフペダル
⑦ロングペダル